第7回お茶づくり探検隊(98年2月8日) |
| 2月は山背古道探検隊の山背サロンとして、井手町の氏神さま高神社の社務所をお借りして,茶歌舞伎を催しました。高神社は、山本隊員のおとうさんが宮司さんを勤めておられる神社。
茶歌舞伎は茶香服とも書き、私などは闘茶という名前の方がなじみがあります。明恵上人が茶を栂尾に分播したころから始まったとのことですので、13世紀の初め頃です。
5種類のお茶が順不同に出てきます。まず一煎目を飲んで各お茶に当てられた札を入れます。花鳥風月客の五枚の札がおのおののお茶に当てられています。玉露は花、てん茶は鳥という具合。ここで入札した札は、後で変更できません。すべてのお茶を飲んでから味を比べて当てるというのでないのが難しいところです。 |
 会場の高神社 | |
 使うお茶をよく頭に入れる | ||
 茶の葉丼(ハハハ丼) |
 入札(?)箱 |
 中身はこんな風 |
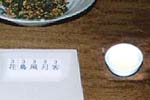 投票札とお茶碗(小振り) |
 競技風景(ただの茶話会?) |
 優勝は平尾さん |
|
|
   後ろのページへ 後ろのページへ
|